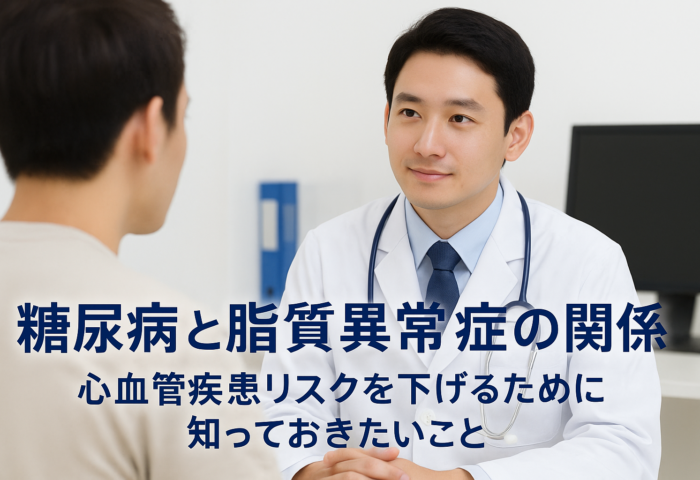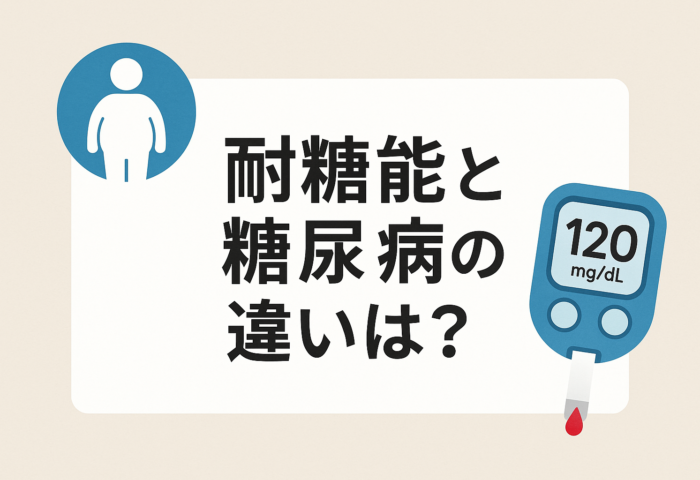糖尿病と脂質異常症の関係―心血管疾患リスクを下げるために知っておきたいこと
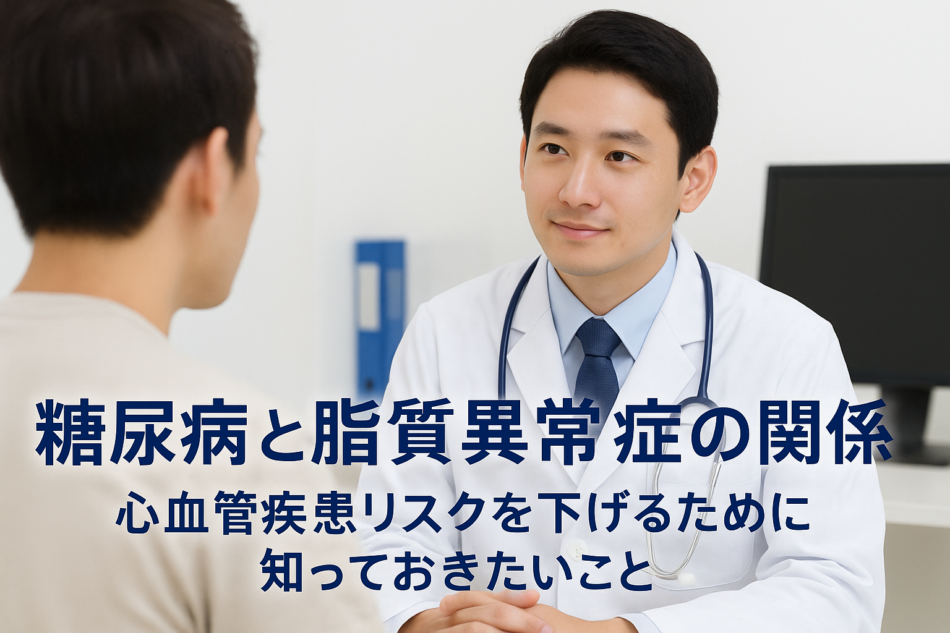
目次
- はじめに
- 糖尿病患者さんが注意すべき脂質異常症とは
- なぜ糖尿病で心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がるのか?
- 脂質異常症が糖尿病合併症にも影響する
- 糖尿病患者さんの脂質管理目標値
- 生活習慣改善が基本―食事療法と運動療法
- 薬物療法の選択肢
- 定期的な検査とモニタリングの重要性
- よくある質問(FAQ)
- 当院での診療について
はじめに
健康診断で「血糖値が高め」「コレステロールが高い」と指摘されたことはありませんか。実は、糖尿病と脂質異常症は密接に関連しており、両方を併せ持つ方は決して少なくありません。特に注意していただきたいのは、この2つが重なることで心筋梗塞や脳卒中といった重大な血管の病気のリスクが大きく上がる点です。
本コラムでは、日本糖尿病学会(2024年版)・日本動脈硬化学会の最新ガイドラインをもとに、糖尿病に合併する脂質異常症のリスクや、どのように管理していけばよいのかを、専門医の視点からわかりやすく解説していきます。
糖尿病患者さんが注意すべき脂質異常症とは
脂質異常症の3つのタイプ
脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが崩れた状態を指します。主に以下の3つのタイプがあります。
- 高LDLコレステロール血症: いわゆる「悪玉コレステロール」が高い状態
- 高中性脂肪血症(高トリグリセライド血症): 中性脂肪が高い状態
- 低HDLコレステロール血症: いわゆる「善玉コレステロール」が低い状態
健康保険組合のデータによると、正常な血糖値の方では高中性脂肪血症が20.9%、低HDLコレステロール血症が4.8%であるのに対し、糖尿病患者さんではそれぞれ50.7%、10.9%と、非常に高い頻度で脂質異常症を合併していることがわかっています(1)。
なぜ糖尿病で心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がるのか?
LDLコレステロールと心筋梗塞の強い関係
複数の大規模研究やメタ解析から、LDLコレステロールは日本人・欧米人を問わず、糖尿病患者さんの心血管疾患の強力なリスク要因であることが明らかになっています。
日本人2型糖尿病患者さんを対象としたJDCS研究では、平均7.8年の観察期間において、LDLコレステロールが標準偏差分上昇すると、冠動脈疾患の発症リスクが1.49倍に増加したと報告されています(2)。また、欧米で行われたUKPDS研究では、高LDLコレステロール血症の患者さんで冠動脈疾患の発症リスクが2.2倍に上昇しました(3)。
中性脂肪とHDLコレステロールの影響
中性脂肪については、研究によって結果が異なりますが、JDCS研究のサブ解析では、中性脂肪の対数値が標準偏差分上昇するごとに冠動脈疾患が54%増加したと報告されています(2)。また、糖尿病を合併した安定性冠動脈疾患患者さんを対象としたBARI 2D試験では、中性脂肪が50mg/dL上昇するごとに心血管イベントが3.8%、心血管死が6.4%増加することが示されました(4)。
HDLコレステロール(善玉コレステロール)については、低いと心血管疾患のリスクが上がることが複数の研究で示されています。特に高中性脂肪かつ低HDLコレステロールの組み合わせは、心血管疾患リスクを大きく高めることがわかっています(5)。
脂質異常症が糖尿病合併症にも影響する
細小血管症(網膜症・腎症・神経障害)との関係
意外に思われるかもしれませんが、脂質異常症は心臓や脳の大きな血管だけでなく、目、腎臓、神経といった細かい血管にも影響を及ぼします。
高中性脂肪血症は、糖尿病網膜症、腎症、神経障害を含む細小血管症のリスク要因です。ある大規模研究では、中性脂肪が1mg/dL上昇するごとに細小血管症のリスクが0.2%上昇し、中性脂肪の目標値150mg/dL未満を達成していた群では、非達成群に比べて細小血管症発症リスクが約15%低下しました(6)。
また、低HDLコレステロール血症も腎症の進行リスクであることが、複数の研究で報告されています(7)(8)。
糖尿病患者さんの脂質管理目標値
個々のリスクに応じた目標設定
日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」では、糖尿病患者さんの脂質管理目標を、心血管疾患の既往や他のリスク要因の有無によって細かく設定しています。
表1:糖尿病患者さんの脂質管理目標値
| リスク分類 | LDLコレステロール目標値 |
|---|---|
| 二次予防(冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞の既往) | 70mg/dL未満 |
| 一次予防でリスク要因あり(PAD、細小血管症、喫煙など) | 100mg/dL未満 |
| 一次予防でリスク要因なし | 120mg/dL未満 |
表2:その他の脂質の目標値
| 脂質項目 | 目標値 |
|---|---|
| 中性脂肪(空腹時) | 150mg/dL未満 |
| 中性脂肪(非空腹時) | 175mg/dL未満 |
| HDLコレステロール | 40mg/dL以上 |
最も重要なのはLDLコレステロールの管理です。LDLコレステロールの目標達成が脂質管理の第一目標となります。
生活習慣改善が基本―食事療法と運動療法
食事療法のポイント
脂質異常症治療の基本は、やはり生活習慣の改善です。食事療法による肥満の改善は、直接的および血糖コントロールの改善を通じて、間接的にも脂質異常症を改善させる効果があります(9)。
効果的な食事の4つのポイント
1. 脂質の質を意識する
飽和脂肪酸(肉の脂身など)を減らし、一価不飽和脂肪酸(オリーブオイルなど)や多価不飽和脂肪酸(魚油など)を適度に摂取しましょう。複数の研究で、魚油に含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸の摂取により、中性脂肪が約40mg/dL低下し、HDLコレステロールが上昇することが示されています(10)。
2. 食物繊維を積極的に
野菜、海藻、きのこ類などに含まれる食物繊維は、LDLコレステロールや中性脂肪を低下させる効果があります。42件の研究をまとめた系統的レビューでは、高食物繊維食がHbA1c、空腹時血糖、LDLコレステロール、中性脂肪、体重などを低下させることが確認されています(11)。
3. 適正なエネルギー摂取
過剰なカロリー摂取は肥満につながり、脂質異常症を悪化させます。適切なカロリー制限により、中性脂肪が有意に低下することが日本人糖尿病患者さんのデータでも示されています(12)。
4. コレステロール摂取に注意
糖尿病患者さんでは、鶏卵などコレステロール含量の高い食品を多く摂取すると、冠動脈疾患の発症や死亡が増加するというメタ解析があります(13)(14)。1日のコレステロール摂取を200mg未満に抑えることが推奨されます。
運動療法による脂質改善効果
運動療法も脂質改善に有効です。2型糖尿病患者さん2,808人を対象とした42件の研究のメタ解析では、監視下での運動療法により、HDLコレステロールが1.5mg/dL上昇し、LDLコレステロールが6.2mg/dL低下したことが示されています(15)。
有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)とレジスタンス運動(筋力トレーニング)の両方が効果的で、週3回程度の運動を継続することで、中性脂肪が79mg/dL、LDLコレステロールが14mg/dL低下し、HDLコレステロールが5mg/dL上昇したという報告もあります(16)。
運動制限のない患者さんには、医師の指導のもとで適切な運動を習慣化することをお勧めします。
薬物療法の選択肢
スタチンが第一選択薬
生活習慣改善だけでは目標値に到達しない場合、あるいは心血管疾患の既往がある高リスクの患者さんでは、薬物療法が必要となります。
高LDLコレステロール血症に対する第一選択薬はスタチンです。14件の大規模臨床試験をまとめたメタ解析では、スタチンによりLDLコレステロールを39mg/dL低下させることで、主要な心血管イベントが21%減少し、この効果は糖尿病患者さんと非糖尿病患者さんで同等でした(17)。また、全死亡も糖尿病患者さんで9%有意に減少しました。
日本人を対象としたCARDS研究では、アトルバスタチン10mg/日の投与により、冠動脈疾患イベントが37%、全死亡が27%減少するという顕著な効果が示されています(18)。
スタチンに追加する薬剤
スタチンだけでは目標値に到達しない場合、以下の薬剤の追加が検討されます。
エゼチミブ
腸管でのコレステロール吸収を阻害する薬です。IMPROVE-IT試験では、シンバスタチンにエゼチミブを追加投与することで、糖尿病患者さんで心血管イベントが14.4%減少しました(19)。
PCSK9阻害薬
非常に強力なLDLコレステロール低下作用を持つ注射薬です。Fourier試験では、スタチンにPCSK9阻害薬(エボロクマブ)を上乗せすることで、LDLコレステロールが92mg/dLから30mg/dLまで低下し、心血管イベントリスクが15%抑制されました(20)。ただし、高価な薬剤であるため、家族性高コレステロール血症や心血管イベントのリスクが非常に高い方が対象となります。
高中性脂肪血症・低HDLコレステロール血症への対応
高中性脂肪血症や低HDLコレステロール血症を合併している場合には、以下の薬剤が検討されます。
フィブラート系薬
中性脂肪を下げ、HDLコレステロールを上げる効果があります。FIELD試験では、フェノフィブラート投与により非致死性心筋梗塞が24%低下し、糖尿病網膜症や腎症の進行も抑制されました(21)。特に、中性脂肪が204mg/dL以上かつHDLコレステロールが34mg/dL以下の方では、心血管イベントが31%低下したというデータもあります(22)。
EPA製剤
魚油由来の成分で、中性脂肪を下げる効果があります。日本で行われたJELIS試験では、スタチンにEPAを併用することで、糖尿病・血糖異常群において心血管イベントが22%減少しました(23)。
膵炎予防のための治療
中性脂肪が500mg/dL以上の高値になると、急性膵炎という重篤な合併症のリスクが高まります。この場合は、禁酒を含めた生活習慣改善の徹底と、必要に応じてフィブラート系薬などの投与が推奨されます。
定期的な検査とモニタリングの重要性
脂質異常症の管理には、定期的な血液検査が欠かせません。LDLコレステロール、中性脂肪、HDLコレステロールの値を定期的にチェックし、目標値に到達しているか、薬の効果や副作用はどうかを確認することが大切です。
また、糖尿病患者さんの場合、血糖コントロール(HbA1c)、血圧、体重なども含めた総合的な管理が心血管疾患予防には重要です。日本で行われたJ-DOIT3研究では、血糖・脂質・血圧の包括的な強化療法により、全死亡、冠動脈イベント、脳血管イベントが24%減少し、特に脳血管イベントが58%も減少したことが示されています(24)。
よくある質問(FAQ)
Q1. コレステロールの薬を飲むと糖尿病が悪化すると聞きましたが、本当ですか?
A1. スタチンによる治療で、糖尿病の新規発症リスクがわずかに増加するという報告はあります(25)。しかし、その増加は軽微であり、心血管イベント抑制や生命予後改善という大きな利益と比較すると、スタチンの使用は明らかに有益です。特に心血管疾患のリスクが高い糖尿病患者さんでは、スタチンによる治療が強く推奨されます。医師と相談しながら、適切に使用していくことが大切です。
Q2. 食事療法だけで脂質は改善できますか?
A2. 軽度の脂質異常症であれば、食事療法と運動療法だけでも改善が期待できます。特に肥満がある方では、体重を減らすことで脂質プロフィールが大きく改善することがあります。ただし、心血管疾患の既往がある方や、LDLコレステロールが著しく高い方では、生活習慣改善と並行して早期から薬物療法を開始することが推奨されます。
Q3. 中性脂肪が高いのですが、お酒は完全にやめないといけませんか?
A3. 中性脂肪が高い方にとって、アルコールは大きな悪化要因です。特に中性脂肪が500mg/dL以上の方では、膵炎予防のために禁酒が必須となります。中性脂肪が150~500mg/dLの範囲であっても、できる限り節酒(1日純アルコール量で男性20g、女性10g以下)することが望ましいでしょう。
Q4. 善玉コレステロール(HDL)を上げる方法はありますか?
A4. HDLコレステロールを上げるには、運動療法が最も効果的です。定期的な有酸素運動やレジスタンス運動により、HDLコレステロールの上昇が期待できます。また、禁煙、適正体重の維持、中性脂肪を下げることもHDLコレステロールの改善につながります。薬物療法では、フィブラート系薬やEPA製剤がHDLコレステロールを上昇させる効果があります。
Q5. 75歳以上の高齢者でも積極的に脂質を下げる治療は必要ですか?
A5. 75歳以上の糖尿病患者さんを対象に、スタチンやフィブラートが心血管疾患発症抑制や生命予後改善に有効であることを示したエビデンスは、現時点では十分ではありません。高齢の方では、個々の健康状態、合併症、日常生活動作能力、予後予測などを総合的に判断し、治療の利益と負担を慎重に検討する必要があります。かかりつけ医とよく相談して、個別化した治療方針を立てることが大切です。
当院での診療について
大阪梅田健美クリニックは、糖尿病と脂質異常症の専門的な連携診療を行っております。日本糖尿病学会・日本動脈硬化学会の最新ガイドラインに基づき、患者さん一人ひとりのリスクに応じた個別化医療を提供しています。
当院の診療の特徴
- 総合内科専門医・抗加齢専門医など、複数の専門医資格を持つ医師が多角的に診断・治療にあたります
- 血糖コントロール、脂質管理、血圧管理を含めた包括的アプローチ
- 最新のエビデンスに基づいた薬物療法の選択
- 栄養士による個別の食事指導
- 定期的なフォローアップと合併症スクリーニング
特に、**他の医療機関で目標値達成が難しかった方、複数の合併症をお持ちの方は、ぜひご相談ください。**保険診療で対応可能な範囲から、必要に応じて先進的な治療オプションまで、幅広くご提案させていただきます。
大阪・梅田で糖尿病や脂質異常症の治療をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
糖尿病に脂質異常症が合併すると、心筋梗塞や脳卒中といった重大な血管の病気のリスクが大きく高まります。特にLDLコレステロールは、日本人・欧米人を問わず、最も強力なリスク要因です。
脂質管理の基本は食事療法と運動療法ですが、目標値に到達しない場合や心血管疾患のリスクが高い場合には、スタチンを中心とした薬物療法が推奨されます。個々の患者さんのリスクに応じて、適切な目標値を設定し、生活習慣改善と薬物療法を組み合わせて総合的に管理することが、合併症予防と健康寿命延伸のカギとなります。
ご自身の脂質の値を定期的にチェックし、主治医とよく相談しながら、適切な管理を続けていきましょう。
参考文献
- Fujihara K, et al. Diabetes Metab. 2017;43:543-546.
- Sone H, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96:3448-3456.
- Turner RC, et al. BMJ. 1998;316:823-828.
- Nelson AJ, et al. Am J Cardiol. 2020;132:36-43.
- Lee JS, et al. Diabetes Care. 2017;40:529-537.
- Toth PP, et al. Cardiovasc Diabetol. 2012;11:109.
- Sacks FM, et al. Circulation. 2014;129:999-1008.
- Russo GT, et al. Diabetes Care. 2016;39:2278-2287.
- Heilbronn LK, et al. Diabetes Care. 1999;22:889-895.
- Hartweg J, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008:CD003205.
- Reynolds AN, et al. PLoS Med. 2020;17:e1003053.
- Shirai K, et al. Obes Res Clin Pract. 2013;7:e43-e54.
- Rong Y, et al. BMJ. 2013;346:e8539.
- Shin JY, et al. Am J Clin Nutr. 2013;98:146-159.
- Hayashino Y, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2012;98:349-360.
- Cauza E, et al. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86:1527-1533.
- Cholesterol Treatment Trialists’ Collaborators. Lancet. 2008;371:117-125.
- Colhoun HM, et al. Lancet. 2004;364:685-696.
- Cannon CP, et al. N Engl J Med. 2015;372:2387-2397.
- Sabatine MS, et al. N Engl J Med. 2017;376:1713-1722.
- Keech A, et al. Lancet. 2005;366:1849-1861.
- ACCORD Study Group. N Engl J Med. 2010;362:1563-1574.
- Oikawa S, et al. Atherosclerosis. 2009;206:535-539.
- Ueki K, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5:951-964.
- Sattar N, et al. Lancet. 2010;375:735-742.
執筆者プロフィール
平山 尚(Hirayama Takashi)医師
医療法人奏仁会 理事長
大阪梅田健美クリニック
【保有資格】
総合内科専門医/泌尿器科専門医/性機能専門医/性感染症専門医/透析専門医/抗加齢専門医/日本医師会認定産業医
【専門分野】
生活習慣病、医療ダイエット、再生医療、EDを含む性機能障害、AGA、性感染症、男性不妊、睡眠時無呼吸症候群、男性更年期障害、